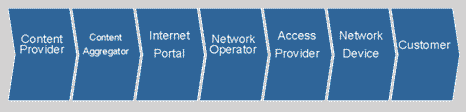|
August 28, 2004
Celebrity Endorsement 1年日本にいなかったので話題が古い・・・けれど、明治のアーモンドチョコ、TBCと聞いて思い出す人は誰でしょうか? 2002年のWorld Cupで人気が高騰したDavid Beckhamですねー。 有名人を使って自社商品/サービスをPromoteする方法は古くからよく用いられていてMarketing用語で"Celebrity Endorsement"(つまり有名人にその商品/サービスの良さを保証してもらうこと)という。 パッと思いつくだけでも飲料業界(伊藤園「おーい、お茶」の中谷美紀、キリン「生茶」の松嶋奈々子)や携帯電話業界(Vodafoneの仲間由紀恵とベッキー、DoCoMoの長谷川京子と坂口憲二)などは"Celebrity Endorsement"がよく使われる業界のよう。 有名人を使うことによってそのブランドの知名度、イメージを高め購買行動に結びつけるのが目的だが、問題点も多い。 1. 有名人があまりにも多くのCMに出すぎているため効果が薄れてしまうケース(上記のベッカムはよい例で、他にも一時期の山口智子、松嶋奈々子など"CMの女王"と呼ばれる系はこの傾向あり) 2. 有名人と商品/サービスの間に何の関連性もないケース(子供を生んだタレントをおむつのCMに使ったりするのはこれの逆パターンで関連性をうまく使おうとしているケース) 3. 有名人がトラブルを起こしたり巻き込まれたり人気を失ったりしたため、そのMarketing Valueが下がるケース 4. 消費者は有名人がお金のために広告・宣伝を行っていると感じているため購買行動にまで結びつかない、さらにはそのような広告・宣伝費が商品価格の中に含まれているので他社製品より価格が高いはずだ、と思い込むケース 5. 有名人のみに気を取られ"CMは覚えているが何の商品だったか思い出せない"というケース(最もよくあるケース) 私が思いつくところでは上記のような問題点を克服して今も覚えている(消費者である私の記憶に残っている)のはサントリーBOSSの矢沢永吉、NISSANのイチローくらいかなー? なお、フランスでは(単に私がフランスの有名人を知らないだけでなく)CMにこんなに有名人を使っていなかった気がする。何となく「横にならえ」的な日本人に利く手法である気がするけどどうなんでしょうか? posted at 12:59 PM : | August 25, 2004 Branding フワフワしていた私好みだったP4の"Advanced Brand Management"のクラス。個人的には「ブランド志向」よりはコスト・パフォーマンスとデザイン(見た目)を重視する方だと思うけれど、ブランドの何が面白いかというと目に見えないintangibleな"ブランド"という ものに相当のお金を払う人がいる(企業側としては"ブランド"が価値を生み出している)という事実とその持つ力に興味があったから。 改めて「"ブランド"って何?」と問われると回答に困る人が多いと思うけれど、"Strategic Brand Management"のテキストではこんな説明をしてます。 "the key to creating a brand is to be able to choose a name, logo, symbol, package design, or other attribute that identifies a product and distinguishes it from others" (page 3) そしてどんなものでも"ブランド"にできるのか?という疑問に対してはこんな例をあげている -(物理的に見える)商品・・・最も馴染みがある、TOYOTAのカローラなど -サービス・・・JAL、クロネコヤマトの宅急便、Club Medなど -流通業・・・伊勢丹、LAWSONなど -オンライン上の商品/サービス・・・Googleなど -人、組織・・・栗原はるみ(男性は知らないか・・・)、UNICEFなど -スポーツ、芸術、エンターテイメント・・・Real Madrid、『冬ソナ』のヨン様など -地理的場所・・・スペインIbiza島 -理念・・・赤十字の赤い羽根など 要はどんなものでもブランドになる、ということ。強力なブランドの作り方についてはまた今度。 posted at 11:01 PM : | August 24, 2004 Critical Mass 前職で苦労したことと密接に関係していた(というかそのものだった)ため、P4のICA (Industry & Competitive Analysis)の3回連続のクラスで雷に打たれたようになった言葉がciritical mass。日本語では「臨界値」と訳される。商品/サービスの供給量がある一定水準を超えると、一部の社会的現象や一過性の流行としてではなく、急速に市場での普及が拡大するようになるが、このレベルのことを言う。 以前述べた"network externality"の現象が働いて起こるケースが多い。社会現象としてまだ記憶にも新しいのがNTT DoCoMoのi-modeの成功。1998年2月にスタートし、加入者数100万人に達したのが半年後の8月、この頃から雪だるま式に「加入者が新たな加入者を呼ぶ」好循環に入り、サービス開始からわずか1年半で加入者1,000万人に達した。NTT DoCoMoの好業績に貢献したのみならず日本=モバイル通信事業先進国の地位を揺るぎないものにした事象として伝説化した。 家庭用TVゲーム機市場では後発だったSony Play Stationが圧倒的スピードで先行者であった任天堂に追いつき追い越し、セガを市場撤退に追い込むまでに市場シェア獲得に成功したのも ゲームソフトが1本数千円と子供のおこづかいでは高額なため友人間で貸し借りをすることになる -->友達と同じゲーム機を買う必要がある という"network externality"が働き、ユーザー数が一定数に達した時点で一気に爆発する、という過程をたどったものだった。 これは市場で先行者ではなくてもcritical massに到達することができるいい例だと思う。 posted at 11:31 PM : | August 23, 2004 Value Chain
Strategyのクラスでは必ず出てきたのがValue Chain。 この図はインターネット業界のValue Chainであり、例えばAmazonで買える音楽CDを考えるとわかりやすい。Content ProviderはBeyonceなどのアーティストであり、アーティストを抱える音楽レーベルであるSony Music。Content Aggregatorはその音楽CDをネット上でユーザーが買えるような形にしたAmazonであり、Internet Portalはユーザーが直接Amazonのサイトにアクセスした場合はAmazonだし、Yahoo!やGoogleなど検索サイトを使った場合はこれらも含まれる。 Network OperatorはNTTのADSLを使用してインターネット接続した場合にはNTTとなり、Access ProviderはBIGLOBEやso-netなどのISP。Network DeviceはPCメーカーであるSonyやAppleで、それら端末を物理的インターフェースとして一般ユーザーに届けられる。 Value Chainは「この業界はこのValue Chain」という絶対的なものでもなければ、上記のInternet Portalの説明でサイトオーナー、検索ポータルの2通りの解釈があると述べたように限定的なものでもない。 ある業界の中でのplayerを洗い出し、どのlayerがユーザーに対してどのようなvalue(価値)を生んでいるのか、どのlayerに力があるのか、言い換えるとvalue(価値)をcaptureしているのか、を把握するためのツールで、では、valueをcaptureしていない(平たく言うと儲かっていない)layerはどうすればいいのか、などの戦略を考えるのに役に立つ。 MBAではこのようにツールを習うことが多く、それをどのように実際の業務でいかせるかどうかは本人の心がけ次第(という私は今日が新しい仕事の初日でした)。 posted at 11:05 PM : | August 20, 2004 Electronic Resources INSEAD時代、今から思えばあれほど勉強したことはなかったけれど資料を調べてPaperを仕上げるのにオンラインのElectronic Resourcesをよく使った。 まず業界分析をする際によく使ったのが次の3つ。 Datamonitor Business Information Center Euromonitor - Global Market Information Database Forrester 特にForresterは広くテクノロジー・IT業界についてup to dateなリサーチが見つかるので重宝。 そして業界ではなく企業の業界での位置付け、財務情報などを知りたい時に役立つのが次の3つ。 Factiva Hoover's Online Thompson One Banker Analytics 日本でいう「会社四季報」のさらに充実版ってところで、就職活動にも使える。 経済界のニュースを検索したい時はやはりこの2紙。 Financial Times Wall Street Journal 日本人であればさらに日経新聞が加われば怖いものなし。 これらのElectronic Resourcesを利用するにはMembership Feeを払わなければならないところがほとんどだけれど、大企業であれば広報などの部署に聞いてみると意外と法人として入っていたりするものです。自分のいる業界や企業を第三者研究機関が分析したものを読むというのも結構新鮮なもの。お勧めです。 posted at 4:32 PM : | August 19, 2004 Positioning 私の興味の対象からしてどうしてもStrategyで学んだ言葉が多くなってしまうけど、今回はINSEAD名物教授 Professor Ingemar Dierickxが教えたNegotiation Analysisのクラスから。P4,P5という学生がだらけて授業に行かなくなることも多い時期に行われたこのクラス、しかも1時間半のほぼ一方的な講義にも関わらず教室はいつも満席だった。残念ながら私たちが(60歳を超えた)教授が教える最後のクラスだったらしい。 このクラスではほぼ毎回NegotiationのセッティングとNegotiationを行う相手の名前が与えられ、その結果をコンピューター上でinputしてから内容をreviewする形で授業が行われる(結果はそのまま成績に反映する)。第一回目で私はいきなり最低の成績を取った。 Negotiationの内容は、私がある土地を買いたい買い手でギリシア人のStephanieがその土地を持っている売り手。それぞれに対して状況説明の紙が与えられ売り手には「この値段以上では買わない」というwalk-off price(交渉決裂価格)、買い手には「この値段で土地を買った」というwalk-off priceが与えられる。 私の持っている情報はというと、その土地そのものは小区画で家が建てられる広さはないので€60Kの価値しかないけれども、自分の持っている隣の土地と合わせると家が建てられる広さになり€150Kの相場価格になる、というもので、€60K-150Kの間で決着をつけることをとりあえずの目標とした(この目標価格をtarget priceという)。 交渉開始後、私はすぐに€75Kのオファーをした。この価格であれば€60Kというその土地だけを見た適正価格よりも大きいのだからStephanieも満足のはず。これに対してStephanieが出したcounter offerは€250K。あまりに差が大きいので€150Kのラインさえ守れればいいか、と安易に考えてしまい、その後タイの土産物屋と観光客のような何の根拠もない価格だけを論点として交渉を重ねて€135Kで決着した。 ところが、(100人以上がこのクラスを取っていた)平均決着価格は€70K前後、そして売り手に与えられていた情報は「10年前に€15Kでこの土地を買った」というものでStephanieは€15K以上であれば売る気だったことが判明した。ここで私が犯した致命的なミスは「自分から最初のオファーをした」こと。自分のreference price(参考となる価格。この場合€60Kや€150K)がわかっていても相手のreference priceが皆目検討がつかない場合にはまず相手と自分の位置関係を決定すること(positioning)が重要。この場合なるべく自分が有利になるようにpositioningすることが必要で相手のreference price(相手が落としどころとしようとしているtarget priceや「この値段以下では売らない」というwalk-off price)を探ることから交渉を始めなければならない。 まさか相手の買値が€15Kだったとは想像だにしなかった私は自分から€75Kのオファーをすることで自分に不利なpositioningにしてしまった。どんな形であれNegotiationの極意とは「自分のことはしゃべらず相手のことを聞く」ことらしい。(相手の家族構成、趣味などを聞くことにより)相手に興味を持っているという態度を示し交渉の場をなごやかな雰囲気にするというのがひとつめの理由、相手の情報を交渉目的(この場合土地の価格)に織り込む(「息子さんが来年大学に進学するのであれば学費も要りようでしょう・・・」など)のがふたつめの理由。 私はこのExerciseで最低の成績を取って以来、「最初のオファーは相手に出させる」ということを目標にしてきた。これは卒業後行ったトルコのバザールでの交渉しかり、就職活動中の給与交渉しかり。両方のケースにおいて「相手がここまでなら譲ってもいい」というギリギリのラインまで交渉できたかどうかは不明(場合によってはギリギリまで絞らない方がその後の友好関係にプラスだったりするし)。でも、明らかにこの"positioning"は知っててよかったことのひとつとなった。 posted at 11:42 AM : | August 18, 2004 Network Externality すでに3日坊主っぽくなってきた・・・けれど、読んでいる人もいるのでがんばります。 "network externality"とは「ネットワーク外部性」などと訳されて、「同じ商品/サービスを消費する人口が多くなれば多くなるほどその商品/サービスの消費から得られる効用が高まる」こと。 早い話が「友達が使ってる」「会社で使ってる」という製品やサービスの技術的優位性、価格競争力などとは別の次元で購入の決断がなされることで、ある特定の企業(もしくはアライアンス)のスタンダードが確立されたり一人勝ち状態を加速したりする状況を説明する言葉。 "network externality"の最もクラシックなケースが1970-1980年代のSonyのBetamaxと松下・ビクターのVHSのビデオテープの規格争いのケース。ハリウッドがVHS陣営につき「VHSじゃないとレンタルビデオが借りられない」という状況になってVHSの勝利が決定的となった。 そしてMicrosoftのWindowsとAppleのMacのOSの規格争い。こちらも「WindowsじゃないとWordやExcelなどのファイルのシェアが不便」という"network externality"が作用してビジネスユーザーに食い込んだWindowsに軍配が上がった。 ネットワーク時代の今日、"network externality"が働くケースは多い。NTT DoCoMoのFOMAも友達がFOMAユーザーじゃないとTV電話etc.ができないので全く意味がない。加入者数が100万人を突破したと聞いてN900iを購入してみたけれど(i-modeの時も100万人突破時点で買った)、ちっとも持っている友達がいないので使えない。「3Gを持ってなきゃ不便」という状態にはまだしばらくかかるのかなー? posted at 11:28 PM : | August 15, 2004 Opportunity Cost "sunk cost"と並んで私がINSEADで学んだ中で最も頭に残っている概念が、"opportunity cost"。Aの選択をすることで犠牲にしなければならないBの選択にかかる費用のこと。 一番ふさわしいのがタイガー・ウッズがスタンフォード大学を中退した例。アマチュアゴルフですでに頭角を現していたタイガー・ウッズにとって「そのまま大学にいて勉学を続ける」という選択肢を取ることは、学費がかかるとかいうことだけでなく、「プロとして年間数億のお金を稼ぐ機会を逃す」=数億という"opportunity cost"を払っている、というのがこの概念。 もうひとつの例もよくあるケース。 最近は子供を託児所やベビーシッターに預けるのに月十数万円という費用がかかるけれど、キャリアを積んだAさんにとっては「仕事を辞めて家で24時間子供といる」という選択をすることは、そのまま働き続ければ得られる月手取り30万円の"opportunity cost"を支払っている、に匹敵するということ。 「MBA留学中に得られない収入」など"opportunity cost"の例は枚挙にいとまがないけれど、ここで重要なことは、上記の例では「タイガー・ウッズが勉学によって知的好奇心を満たせる精神的満足感」や「常に子供の成長を見守っていられるという安心感」などは金銭以外の要素は考慮されていない。 "opportunity cost"の概念は「犠牲にしなければならない選択肢のコスト」を正確に捉えた上で「さて、それでもどうしようか?」と金銭以外の要素を加えて総合的に決断できるようにする、という意味で知ってた方が何かと便利な考え方だと思う。 posted at 7:50 PM : | August 13, 2004 Sunk Cost P1の初期の授業(『ミクロ経済』だった気がする)で登場し、その後MAC(Managerial Accounting)など、いろいろなクラス、及び学生の間でのBusiness School Jokeでも頻出したのがこの"sunk cost"。 過去にある企業が(企業に限らないが)行った投資は今後この企業がA、Bどちらの決断をしようが取り返しのつかないものなので、本来ならば今後の方向性を決める意思決定に影響を及ばしてはならないはずなのに、「投資額を何とか回収したい」という気持ちが働いて意思決定に影響を及ぼすような場合のことを言う。 具体的には、ある企業が新規にチップを開発・設計する期間を2年間、費用を5億円と見積もり、開発をスタートしたとする。開発期間半年、費用を1.5億円かけた時点で営業サイドから「市場は当初想定していたよりも早いスピードで動いており、競合他社が半年以内に同様の機能を持ち価格競争力のあるチップを出してくるので、我が社が市場に出す頃にはすでに勝負は決まってしまっている」という声があがったとする。 この時点ではA.チップ開発を中止する、B.チップ開発を継続する、という選択肢が考えられる。本来であれば将来の価値を最大化する(もしくは将来の損失を最小化する)ことを決断の基準とすべきであるのに「今開発中止するとすでに投資した1.5億円をドブを捨てることになる。それよりも開発を継続して商品が売れるような戦略を考えるべきだ」と考えてしまうのを"sunk cost"にとらわれた考え方という(ちなみにこの場合「残り1.5年の開発期間」という"opportunity cost"も支払うことになるので二重によくない。"opportunity cost"については次回)。 "sunk cost"にとらわれないのは難しい。私の場合、INSEADのFontainebleau Campusでスタートした。P3は1,2月にあたり、ほとんどすべての仲のいい友達が常夏のSingapore Campusに行くことを決めたのに(INSEADではP3以降は自由に2つのキャンパスを行き来できる)「すでに1年間分の車のリース代を払ってしまった、家賃を二重に払わなければならない」という2つの理由から(それだけじゃないけど)Fontainebleau Campusに残ることにした。周囲からは「そんなのsunk costだ」とさんざん説得を受けたのに・・・ そしてすべてが終わった今振り返ってみると、私が将来にわたって付き合っていくだろう友達は全員P3にSingaporeに行っていて「P3がINSEAD生活の中で一番楽しかった」という。私のP3はというと、寒くて暗いFontainebleauの森の中、Homesick、Friendsickに襲われるというINSEAD生活の中で最もイケテナイ日々であった。 人生に照らして考えてみても"sunk cost"にとらわれているように思えることは本当に多い。「せっかく○○大学に行ったんだから、この大学じゃないと入れないような有名企業に入らなければ・・・」「せっかく新しいゴルフクラブを買ったのに、時間がないからと行かないのはもったいない・・・」 過去の投資に縛られてすぎて将来の価値を最大化(未来の幸福を最大化)するチャンスをみすみす逃してないかなー、とこの"sunk cost"を知って以来よく考える。 posted at 9:34 PM : | August 11, 2004 INSEADカリキュラム 今後よく出てくると思うのでINSEADでのカリキュラムについて紹介します。 アメリカのビジネススクールでは学期はTerm制だったりSemester制だったりするのでしょうが、INSEADは全部で10ヶ月間という短いプログラム。2ヶ月を一単位としてPeriodと呼ばれ、5 Period(P1-P5)で終了です。 Core Course(必修科目) □P1 Prices & Markets(ミクロ経済) Financial Accounting(財務会計) Financial Market & Valuation(ファイナンス 1) Uncertainty, Data & Judgement(統計) Leading People & Groups(組織論 1) □P2 Foundation of Marketing(マーケティング) Strategy(戦略) Process Operation & Management(オペレーション) Managerial Accounting(管理会計) Corporate Finance Policy(ファイナンス 2) Leading Organization(組織論 2) □P3 Macroeconomics(マクロ経済) International Polytical Analysis(国際政治) Information Systems Management(IT) Elective(選択科目) □P3 Financial Statement Analysis Corporate Renewal & Entrepreneurship Internet & its Prospects □P4 Advanced Brand Management Industry & Competitive Analysis Negotiation Analysis Value Creating Management in Media □P5 Global Strategy & Management Managing Entrepreneurial Growth Marketing Communication 一見してわかるように選択科目ではMarketingとStrategyの授業を中心に取ってしまったので、頭の中に残っているのもこの2つが中心になると思います。いまさらながらEntrepreneurshipの授業を何か取っておけばよかったな・・・と少し後悔しています。 posted at 11:57 PM : | August 10, 2004 はじまり、はじまりー 2004年7月にフランスのINSEADというビジネススクールのMBAを取得し日本に帰国しました。 10ヶ月という短期間のプログラムを無呼吸短距離走のように駆け抜けた生活が終わり、「私にとってINSEADとは何だったのか」を見つめる日々が続いています。あまりにプログラムがIntensiveだったため、授業についていくこと、落第しないことに必死だったというのが正直なところで、学んだ内容を噛み砕いて自分の血・肉にできたというのには程遠い状況です。そんな中でも「MBAとは言葉(ことば)だ」ということを知ったのが大きな収穫。そこで、毎日ひとつ私がINSEADで学んだ言葉(ことば)を取り上げ、それを使って日々の生活やビジネスの事象を説明することを試みることにしました。 このWeblogの書く目的は2つ。 1. Weblogを自分に義務づけることでINSEADで学んだことの復習を課し、今この瞬間も私の脳のキャパから溢れ出て忘却の彼方へと送られつつある知識をしっかりと脳内に留め、さらに実生活で使えるようにする 2. 今後MBA取得を考えている人に「MBAに行くとつまるところ何を身につけられるのか」の感触をつかんでもらい、今後の方向性決断の一助としてもらう なお、内容はあくまで(留学までビジネス本も読んだことがなく、コンサルタントのようなMBAっぽい(?)ビジネス経験もない)私が持てるキャパシティーをすべて使って得たものなので、あくまで個人的な体験だという点をご了承ください。 留学中のWeblogについてはコチラでどうぞ。 -->l'année à fontainebleau posted at 12:04 PM : | |
||||||||||||